|
 |

『続殺人狂時代』 本多劇場/2004
|
|
■ 『寿歌』と『寿歌 II』 北村想とは同世代なので、時代感覚には共通のものがある。60年代から70年代の負の二大因子は、公害と核戦争だった。当時は人類滅亡、世界の終焉の恐怖が意識の底流にあった。知人の中には北半球の壊滅を予期して、南半球への移住を真剣に考える者もあった。事ある毎にシカゴ大学の核の時計の針が進むという時代だった。大学闘争の挫折を経て、「明るい虚無感」という作者の言葉と共に、『寿歌』の終末感は醸成された。 舞台は、核戦争後の関西。旅芸人の一座の生き残りが瓦礫の原で、リヤカーを引いている。時折遠方で残りのミサイルが爆発する。原色に光るこれらを花火に見立てる感覚が鮮やかだ。キリストを連想させるヤスオ (ヤソ=耶蘇) と名乗る人物との遭遇と別離の後、放射能の灰の混じる降雪の中、リヤカーはモヘンジョ・ダロ (死者の丘)を目指す。 |
 モヘンジョ・ダロ |

『寿歌』 矢野健太郎 CKホール/1989
|
|
■『その鉄塔に男たちはいるという』 ある共同体が外部と対立する状況下、内部に巻き起こる葛藤と矛盾を、軽妙な会話のやりとりで展開する。土田作品の多くに見られる構成と作風が踏襲されている。この共同体が彼らの劇団MONOと二重写しに見えて、集団論としても受け取れる巧みさが見事である。主宰者の苦悩が偲ばれる。 |
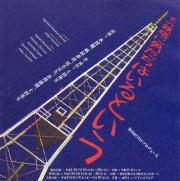 |
 『その鉄塔に男たちはいるという』 ザ・ポケット/2001 |
|
幕切れは、バリー・マクガイアの唄う『明日なき世界』(原題は『Eve of Destruction』)。これに砲声を混ぜ、カーテンコールへと繋いだ。武力とコントが対峙するという着想が奥深い。
|
