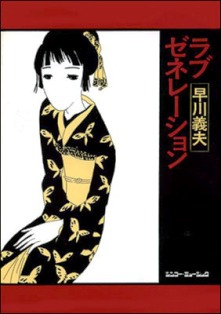 |
|
劇中の音楽や効果音の使い方に、決まり事はない。戯曲・俳優・装置・照明などとの相関の中で決められる。音響プランを作るのは、演出的な行為であるというのが適切だろう。絵画に例えれば、何を描くのも自由だが、額縁の形と画布の大きさとは、予め定められているというのに近い。
舞台の上の音は、大きく四つに分けることができる。
(1) 俳優の発する声や物音
(2) 歌や踊りに付随する音楽
(3) 環境・状況の説明や、物語の進行のための効果音 (例 : 波/電話/銃声/近所のピアノ)
(4) 台詞に掛かる音楽や転換時の音楽
ここでは、取り敢えず、生音(なまおと)と再生音とを、区別しない。
■『寿歌』(ほぎうた)
『寿歌』(作=北村想) には、ミサイルと蛍が登場する。景二は「火垂」(ほたる)という題がついている。音を考えた場合、ミサイルはいい。困ったのは、蛍である。蛍は、作品の中で、<空蝉と幻>を媒介する重要な役どころである。蛍は鳴かない。これを何とか、音響的に表現できないかと考えた。行き当たったのは、"風鈴" であった。稽古で使ってみると、淡い蛍の光が点滅する感じと、弱く鳴る風鈴の音色は適合した。暗い中で響くそれには、幻の如く儚い美感があった。後段の蛍が増殖する件には、金属的な打楽器の音を用いた。粒子感のある音で、"風鈴" と連携の取れた音の構成ができた。
 |
この作品は、初演(1979) から20年を経た現在も、作者自身の演出で上演される機会がある。この間、音響プランも幾多の変転を重ねた。ト書きに指定されている、ザ・ピーナッツの『ウナセラディ東京』は降板したが、この風鈴の音は健在である。 『ウナセラディ東京』1964 |
|
 写真提供=大野城まどかぴあ |

| 劇中、7曲程音楽を使った。終幕は、沖縄の歌手・平安隆の『月』という曲で閉じた。佳曲である。語呂合わせもあったのだが、島唄を使うことで、小空間では希薄になりがちな、島の風土や歴史性といった部分を、補完できると考えたからだ。美術の奥村泰彦も、居間の畳に琉球畳を指定してきた。やはり<南方>というイメージがあったそうである。当初、他に2曲の八重山民謡を予定していた。だが、演出家から違和感があるとの指摘を受け、沖縄音階の器楽曲に変更した。 |
|
 『植物文様』藤枝 守 TZADIK 7025 『植物文様』藤枝 守 TZADIK 7025 |
こうして、沖縄音階と純正調、そして平均律の三つの音楽が、代わる代わる立ち現われることになった。最後の場面では、「萩の花が咲きましたね」という台詞をきっかけに、前出の『月』の前奏が始まり、一分程経って、最後の台詞を言い終わると、丁度、歌が始まるという趣向である。歌を使ったことは、それが抱える世界性によって、劇の世界を相対化する作用をもたらした。単調さを避け、音が作品の世界に広がりを持たせるように心掛けた。
■ 演劇の音響プランとは演劇の音響プランにおいて、個々の音は、全体のプランの一環である。場面に合わせて、曲の進行やテンポを編集・調整するので、原曲が丸ごと使われることは稀だ。個々の音曲は素材である。生け花における花のようなものと理解してもらえばよいだろうか。ミックスして使う場合も多い。現場では、音質・方向性・距離感などが調整される。音量・音像などは舞台の進行に合わせて、オペレータの手により、コントロールされる。 演劇の音響は、ただ雰囲気を作ったり、効果的といった効能だけで用いられる訳ではない。音響プランは、選曲という行為を内包するが、それとは別物だという事を、分かって戴ければ幸である。
(悲劇喜劇 2001年4月号より/特集=演劇界の新たな胎動)
